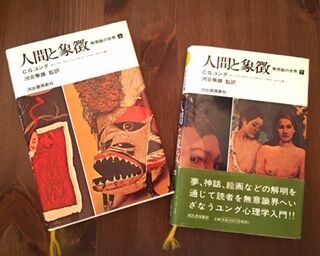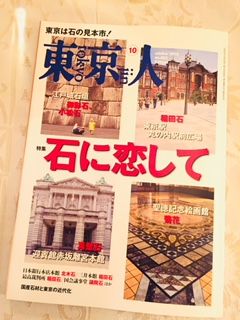舞台はレトロな喫茶店。店の主たちと店に訪れる客たちが体験する不思議であたたかなストーリーが連なります。
「助けて、誰か助けて・・・・・・」
そんな想いにかられたとき、なぜか誘われるように喫茶店を訪れることに。その喫茶店のスイーツには、悩める者へのヒントが秘められているのですが、悩める客が体験するのは、そのスイーツを縦糸に時空を超えた世界。それは決まって店の大きなふるどけいが、いつもと違った響きを奏でるときに展開されるのです。
この作品を読みすすめていて、ほろりとしたところがあります。それは、店主ハツ子が、毎年7月になるとこっそりトマトジュースのクリームソーダを作って飲む、というくだり。そのメニューを店で封印してきたのは、亡くなった幼い妹との思い出があるから。妹が亡くなる二ヶ月前の夏、妹とクリームソーダを半分ずつ分け合って楽しんでいたのです。食べ物からある情景を思い出す、ということは誰もが経験することと思いますが、私にもしばらく手が出なかったスイーツがあります。そのスイーツを見ると、ある記憶が蘇ってしまうからでした。
店主ハツ子が封印してきたクリームソーダは、悩める客の背中を押すことになります。そして、ハツ子の気持ちもまた切り替わっていくのでした。
人は、過去に流せなかった涙があると、先に進めなくなってしまうこともある、と思います。誰かに話すことで、胸の奥に沈殿してしまった澱のようなものが溶けていく、そんなシチュエーションを提供するレトロな喫茶店の物語を通して、読者の私の気持ちもまた、ほぐれていくのがわかりました。
自分の本音を言えない子供、親の介護に苦闘する娘、闇バイトに加担させられそうになった青年、そんないろんな想いを抱える人たちが、喫茶店の不思議な世界では、別の誰かに成り替わっていて、自分を俯瞰してみることができるようになるというしかけがあります。悩みの渦中にあるときは、この俯瞰して考えるということがなかなか出来ないものだと思います。ポジションが替わることで、今まで見えなかったものが見えてくる、そういう変化の様子に思わずほっとして、あたたかな気持ちになります。
この物語には、バックに音楽が流れるシーンがあります。それは時を超えた昭和の一コマを象徴する蓄音機から流れるもので、私は再び本を片手に、You Tubeで音楽を流しつつ作品を楽しんでみました。まるで自分もその場にいるような臨場感が味わえること間違いないです。
時を超えて意識で繋がる感覚、そして共鳴出来る物語にきっと出合える事と思います。
『レトロ喫茶おおどけい』 双葉文庫 2023年8月9日発刊
内山純 氏 プロフィール
1963年生まれ。2014年『B(ビリヤード)ハナブサへようこそ』で第24回鮎川哲也賞を受賞しデビュー。他の著書に『土曜はカフェ・チボリで』『新宿なぞとき不動産』『みちびきの変奏曲』
作者インタビュー記事
https://colorful.futabanet.jp/articles/-/2393
↓ ↓ 応援よろしくお願いします![]()
![]()